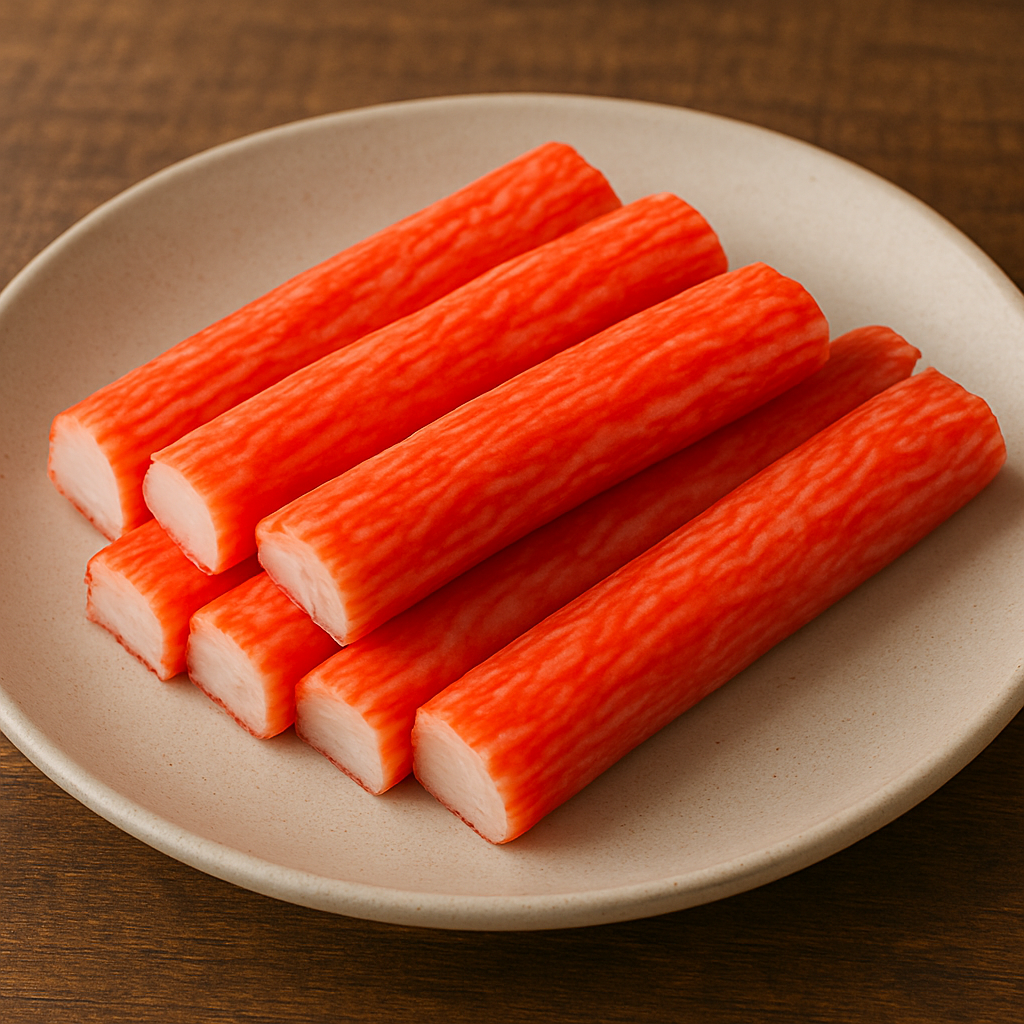カニカマは手軽で美味しい加工食品として多くの人に親しまれていますが、「添加物が多そう」「塩分や糖質が心配」と感じたことはありませんか?この記事では、カニカマの製造過程や含まれる成分、健康への影響、そして健康的に楽しむためのポイントまでを分かりやすく解説。おすすめ商品やレシピも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!
1. カニカマってどんな食品?

カニカマは、スーパーのお惣菜コーナーやお弁当の定番として、すっかりおなじみの食材です。安価で手軽に使えることから、日常的に口にしている方も多いのではないでしょうか。
しかし、その正体や作られ方を詳しく知っていますか?恥ずかしながら私もよく知らなかった一人です。この章では、カニカマの基本情報や人気の理由、製造過程についてわかりやすく解説します。
1.1. カニカマの原材料と作り方(代表的なメーカーの製造過程)
カニカマ(かに風味かまぼこ)は、主に白身魚(スケトウダラなど)のすり身を原料に作られた加工食品です。カニのような食感や風味を再現するために、調味料や着色料を加え、成形し加熱して製造されます。
カニカマの元祖ともいえるのが、石川県の食品メーカー「スギヨ」。1972年に世界初のカニカマ「かにあし」を開発しました。現在では「香り箱 極」など、よりカニに近い風味を追求した商品も展開しています。
スギヨのルーツは、加賀藩治世の時代までさかのぼります。能登半島の七尾で網元として漁業を営んでいた
出典:スギヨトップ>知る・楽しむ>スギヨの歴史
杉野與作が、幕末に「杉與(すぎよ)」の屋号を使い始めたのが現在の「スギヨ」の始まりです。
明治初年からブリなどの定置網漁のほかに鮮魚問屋を兼業するようになりました。
さらに、カニカマ製造機を世界に広めたのが、山口県の食品機械メーカー「ヤナギヤ」。1979年に開発された自動製造機は、世界シェア70%を誇り、今でも多くの工場で使われています。
戦後日本で「食品の三大発明」と言われるものがある。インスタントラーメン、レトルトカレー、カニカマだ。その中のカニカマを作る装置で、世界シェア7割を誇るのがヤナギヤ(山口県宇部市)。創業100年を超える長寿企業だ。柳屋芳雄社長は、ユニークな経営哲学で独自のものづくりの道を追求している。
出典:ニッポンドットコムHome>トピックス>カニカマ製造装置で世界シェア7割―ヤナギヤ : ニッチな市場でとことん顧客に寄り添う製品開発とメンテナンス
これらの製造過程を経て、安価で手軽に食べられるカニカマが私たちの食卓に届いています。
1.2. 手軽で便利、人気の理由とは?
・そのまま食べられる
・サラダや弁当に彩りを加えられる
・価格が安く、保存も効く
以上の理由から、カニカマは家庭でも外食産業でも幅広く使われる人気食材となっています。
2. カニカマが健康に悪いと言われる理由
手軽で美味しいカニカマですが、ネットやSNSでは「健康に悪いのでは?」という声も見かけます。その理由は、加工食品ならではの特徴や、含まれている成分にあります。この章では、そうした疑問の背景にある具体的な理由について、わかりやすく掘り下げていきます。
2.1. 食品添加物が多く使われている
市販のカニカマには、保存料、着色料、リン酸塩などの添加物が含まれていることが多いんです。これらは製品の色味や風味、保存性を向上させるために使われますが、摂りすぎには注意が必要です。
添加物については、こちらの記事もぜひ。
2.2. 塩分や糖質が意外と高め
カニカマ100gあたりの塩分は約2.2g。成人男性の1日摂取目安(6.5g)を考えると、数本でもかなりの割合を占めることになります。また、でん粉が含まれているため糖質も意外に多く、血糖値の急上昇を招く可能性も。
2.3. 加工食品としての注意点
添加物や調味料の影響を受けやすい加工食品であるため、他の食品とバランス良く摂取する必要があります。「健康に悪い」と言われるのは、過剰摂取やバランスの悪い食事との組み合わせが原因です。
3. 添加物・塩分・糖質の体への影響
前章でカニカマに含まれる添加物や塩分、糖質が健康リスクにつながる可能性があることをご紹介しました。では、これらの成分が実際に私たちの体にどのような影響を与えるのでしょうか?この章では、それぞれの成分ごとに体への作用や注意点を詳しく見ていきます。
3.1. 添加物の摂りすぎが引き起こす可能性のある症状
・リン酸塩:カルシウムの吸収を妨げ、骨粗しょう症のリスク
・コチニール色素:一部でアレルギー報告あり
・保存料:長期摂取で腸内環境への影響も懸念
厚生労働省や消費者庁も、添加物の使用は安全な範囲内としていますが、摂りすぎは避けるべきです。
3.2. 塩分の過剰摂取によるむくみ・高血圧リスク
・むくみやすくなる
・高血圧のリスクが高まる
・胃への負担も増加
塩分は摂取量のコントロールが大切です。
3.3. 糖質による血糖値の急上昇に注意
・インスリンの過剰分泌
・食後の眠気や疲労感
・糖尿病リスクの増加
糖質制限中の方は、1食で食べるカニカマの量を調整しましょう。
4. 健康的にカニカマを楽しむポイント

しかし、「カニカマ=健康に悪い」と決めつけるのは早計です。実は、選び方や食べ方を少し工夫するだけで、カニカマは栄養バランスの良い食生活に役立つ便利な食材になります。この章では、健康を意識しながらカニカマを上手に楽しむための具体的なポイントをご紹介します。
4.1. 無添加・減塩タイプを選ぶ
商品パッケージ裏の「原材料表示」を確認しましょう。
「リン酸塩」「調味料(アミノ酸等)」「着色料(赤○号)」などが少ない商品がベターです。
4.2. 食べる量を意識する
1日50g程度(2~3本)を目安に。毎食取り入れるのではなく、週に数回の補助的な食材として使うと◎。
4.3. 野菜やたんぱく質と合わせて食べる工夫
・サラダのトッピング
・豆腐や卵との組み合わせ
・炒め物やスープの具に
野菜や良質なたんぱく質と一緒に食べることで、バランスの良い食事になります。
5. おすすめのカニカマ3選
ここではオススメのカニカマを3つ、ご紹介します。
5.1. スギヨ「香り箱 極」
- 添加物すくなめで素材本来の味を活かしたカニカマ
- ズワイガニ風味に近い本格派
- 高級スーパーやネットで購入可
▶本物のカニと見間違うほどの本格派のカニカマを楽天でチェックする
5.2. カネテツデリカフーズ「ほぼカニ®」
- 本物のカニのようなジューシーな食感
- たんぱく質豊富でダイエット中にも最適
- 付属の黒酢だれ付きで味変も楽しめる
▶カニカマといえば!「ほぼカニ」の冷凍500gを楽天でチェックする
5.3. ビオラル「素材そのままおいしいかにかま」
- 無添加に近いシンプルな原材料
- 北海道産すり身使用で高品質
- スーパー「ライフ」や「ビオラル」店舗で購入可能
5.4. カニカマに“完全無添加”が少ない理由と、なるべく添加物を避けるコツ
「無添加のカニカマがほしい」と考える方も多いかもしれませんが、実は市販されているカニカマには、完全に無添加の商品はほとんど存在しません。その理由は、カニカマが魚肉のすり身を加工して作る食品である以上、一定の品質・安全性・日持ちを確保するために、どうしても最低限の添加物が必要とされるからです。
特に以下のような目的で、食品添加物が使用されます:
- 品質保持(保存料・pH調整剤など)
- 食感や見た目の向上(増粘剤・着色料など)
- 味や香りの再現(調味料・香料など)
ただし、「添加物が含まれている=体に悪い」というわけではありません。日本では厳しい基準のもとで使用が許可されており、適量であれば健康に問題ない範囲で使われています。
とはいえ、日常的に口にする食品だからこそ、できるだけ添加物を少なく抑えた商品を選ぶことが安心につながります。選び方のポイントは次のとおりです。
5.5. 添加物をなるべく避けるためのチェックポイント
- 「リン酸塩」「調味料(アミノ酸等)」「着色料(赤●号)」などの記載が少ないものを選ぶ
- 「無リンすり身使用」や「国産原料使用」と書かれている商品を優先する
- 見た目が“鮮やかすぎる赤色”の商品は避ける
こうした視点で商品を選ぶことで、カニカマをより安心して、健康的に楽しむことができます。次の章では、そうした基準を満たすおすすめ商品を3つご紹介します。
6. 簡単でおいしいカニカマレシピ3選
せっかくなら、カニカマをただ食べるだけでなく、ひと手間加えてもっと美味しく楽しみたいですよね。ここでは、栄養バランスを考えつつ、誰でも簡単に作れるカニカマのアレンジレシピを3つご紹介します。忙しい日でもすぐに作れる手軽さが魅力です。
6.1. カニカマときゅうりの中華風和え物
材料(2人分)
カニカマ4本、きゅうり1本、ごま油・酢・醤油 各小さじ1、白ごま
作り方
きゅうりを塩もみして水気を切り、カニカマをほぐして調味料と和えるだけ。
6.2. カニカマなんちゃってカニクリームパスタ
材料(2人分)
パスタ160g、カニカマ6本、玉ねぎ1/2、牛乳200ml、小麦粉大さじ2、バター、塩コショウ
作り方
玉ねぎを炒めてホワイトソースを作り、ホワイトソースをゆでたパスタとカニカマを和えるだけで完成!トマトソースを加えても◎

6.3. カニカマと豆腐のヘルシースープ
材料(2人分)
カニカマ4本、豆腐1/2丁、鶏ガラスープ400ml、ネギ、塩コショウ
作り方
具材を煮るだけの簡単スープで、朝食にもぴったり。
7. まとめ:カニカマは選び方と食べ方次第で健康的に楽しめる
ここまで、カニカマの原材料や健康リスク、選び方のポイントやおすすめ商品、レシピまで幅広くご紹介してきました。最後にもう一度、大切なポイントを整理しながら、カニカマを安心して楽しむためのコツを振り返ってみましょう。
7.1. 健康リスクを知って賢く選ぶ
カニカマには添加物や塩分・糖質が含まれているため、「食べ過ぎ」や「単品での大量摂取」は健康リスクにつながる可能性があります。とはいえ、完全に避ける必要はありません。ポイントは「選び方」と「組み合わせ方」です。
具体的には、次の工夫を意識しましょう。
- 原材料表示をチェックする:リン酸塩、着色料、保存料が少ない商品を選ぶ。
- 摂取量をコントロールする:1日あたり50g(2〜3本程度)を目安に。
- 栄養バランスを意識した組み合わせにする:
特におすすめなのが、「抗酸化作用」のある食品と一緒に摂ることです。以下のような食材が、添加物による負担を軽減してくれると考えられています。
抗酸化作用のある食材の例:
- ブロッコリー・キャベツ(スルフォラファンが解毒酵素を活性化)
- 緑茶・抹茶(カテキンが活性酸素を抑える)
- ごぼう・きのこ類(食物繊維が有害物質の排出を助ける)
- 大葉・生姜・にんにく(解毒や殺菌の働きをサポート)
- レモン・柑橘類(ビタミンCで抗酸化)
例えば、カニカマをキャベツと和えたり、ブロッコリーと炒めたり、味噌汁の具にごぼうと一緒に加えるなど、日々の食卓で簡単に取り入れられます。
こうした工夫をしながら摂取すれば、カニカマも健康的な食生活の一部として活用できます。
7.2. 手軽でおいしい食品としてうまく活用しよう
・手間なくたんぱく質を補給できる
・調理が簡単なので続けやすい
・最近ではヘルシー志向の商品も豊富
日常的に取り入れる際は、全体の栄養バランスを意識しつつ、賢くカニカマと付き合いましょう。
まとめの要点チェックリスト
とはいえ、情報が多くてすべてを覚えるのは大変ですよね。そこで最後に、カニカマを健康的に楽しむための大事なポイントを、チェックリスト形式でコンパクトにまとめました。買い物や調理の際に、ぜひ活用してみてください。
✅ 添加物や塩分の表示を確認して購入する
✅ 無添加・減塩タイプを選ぶ
✅ 摂取量は1日50g程度を目安に
✅ サラダやスープに加えて栄養バランスを整える
✅ レシピを工夫して飽きずに続けられるようにする
最後に

「カニカマ=健康に悪い」と思い込まず、選び方・食べ方を意識することで、毎日の食事に美味しく安全に取り入れられます。今日からぜひ、スーパーでカニカマを手に取るときに、少しだけ裏面表示を見てみてください。きっと、新しい発見がありますよ!